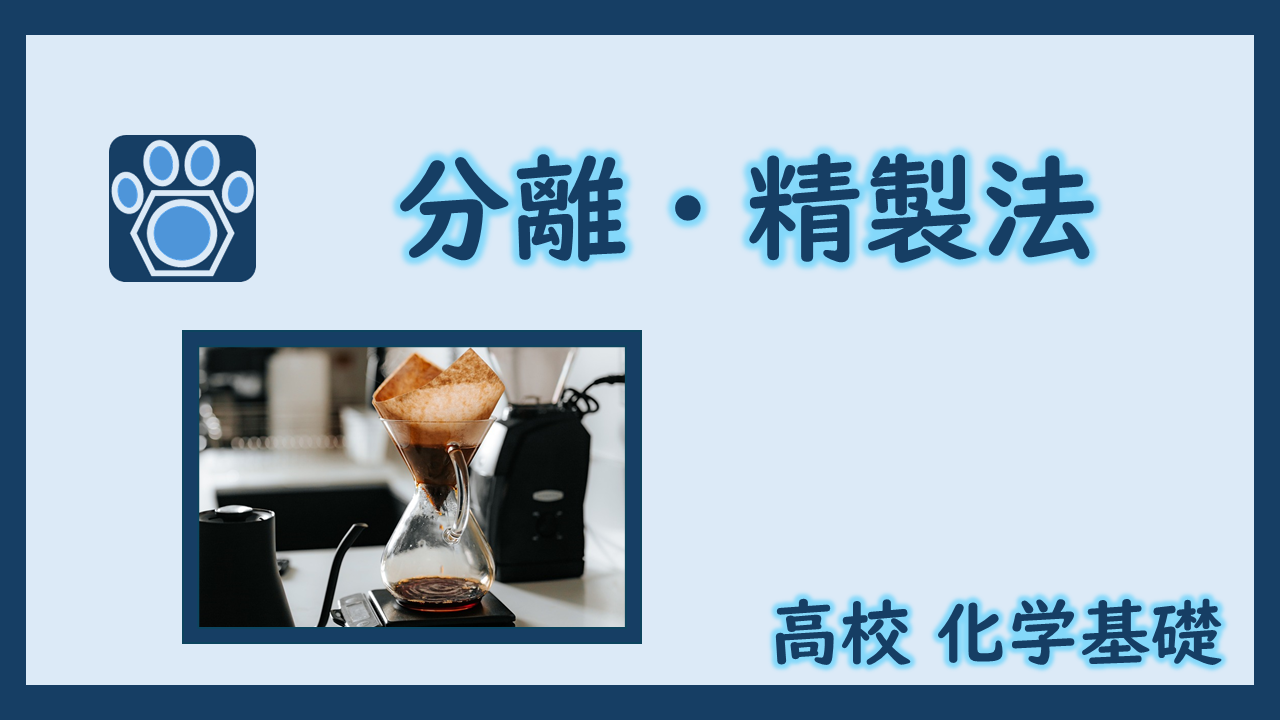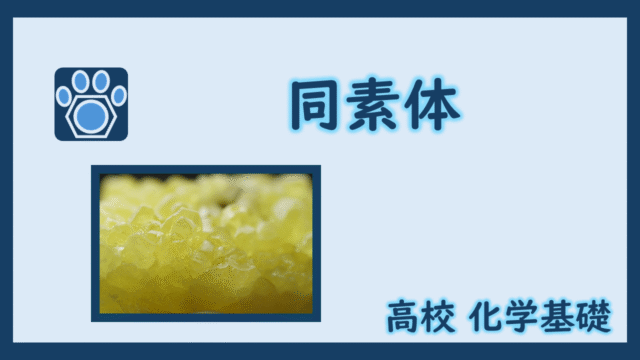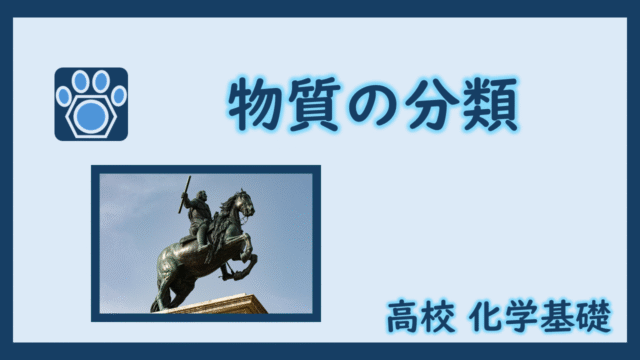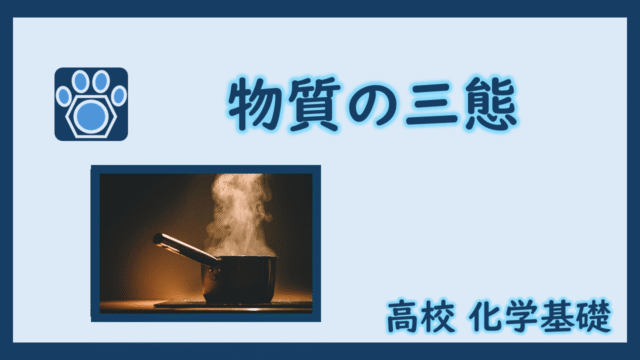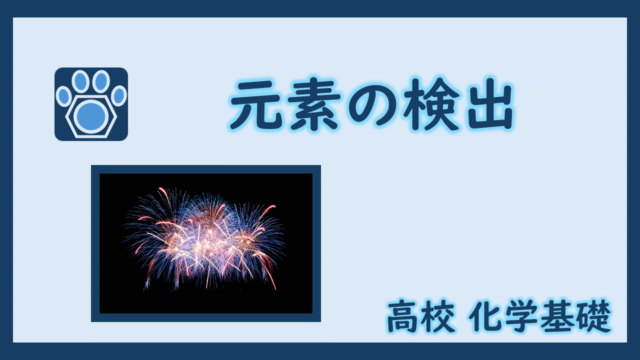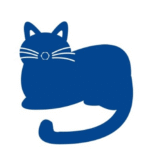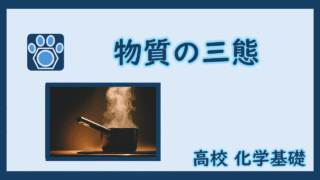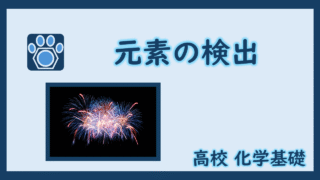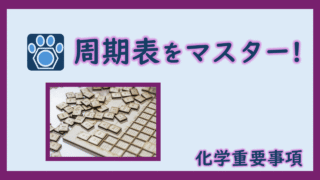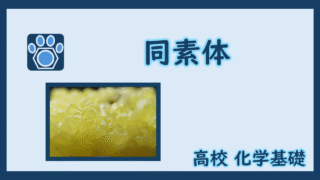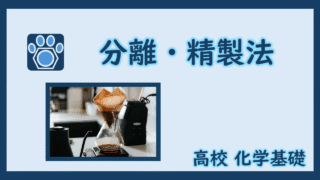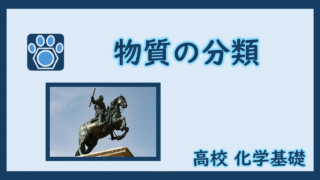【目標】
●各分離・精製法の特徴と使用器具を知る
●分離・精製法の使い分けができるようにする!
化学では、ある物の性質を調べるために純物質について調べます。しかし、この世に存在する物質は混合物であることが多いです。混合物は混ざる割合で性質が変わるので、そのまま性質を調べるには不適当です。よって混合物から純物質に分ける技術が発展しました。その方法を学びましょう。
分離・精製とは
「分離」と「精製」の用語をまずは知っておきましょう。
【分離と精製】
○分離:物質の性質の違いを利用して、混合物から目的の物質を取り出す操作
○精製:分離によって不純物を取り除き、物質の純度を高める操作
分離・精製法の種類をおさえよう
分離・精製法には以下の6種類があります。
①ろ過 ②蒸留(②’分留) ③昇華法 ④再結晶 ⑤抽出 ⑥クロマトグラフィー
1つずつ見ていきましょう。
①ろ過:固体と液体の混合物をろ紙を用いて分離する操作。
ろ過によって通過した液体をろ液という。
②蒸留:固体が溶けた液体の混合物を加熱し、液体のみを気体に変え、冷やすことで再び液体として分離する操作。
②’分留:液体どうしの混合物を蒸留し、沸点の違いを利用して物質を分離する操作。
③昇華法:固体が直接気体になる変化(=昇華)を利用し、固体どうしの混合物を分離する操作。
④再結晶:物質の溶解度が物質と温度ごとに異なる性質を利用し、固体に含まれる少量の不純物(固体)の混合物を、水を用いてより純粋な物質を得る精製法。
⑤抽出:物質の溶媒への溶けやすさが異なる性質を利用し、混合物を2種類の溶媒に溶かして溶液にし、目的の物質を分離する操作。
⑥クロマトグラフィー:物質への吸着力の違いを利用した分離法。
(1)ペーパークロマトグラフィー:紙への吸着力の違いを利用
(2)カラムクロマトグラフィー:シリカゲルへの吸着力の違いを利用